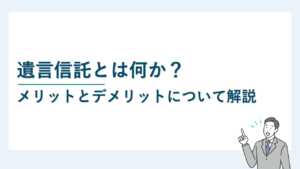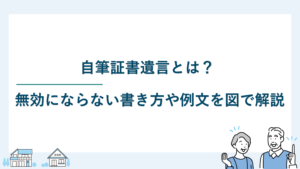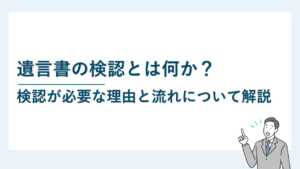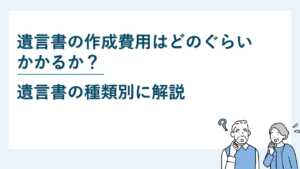遺言能力がなかったのでは?納得できない遺言書への対処法を解説

見つかった遺言書の内容が、生前の故人の意向とかけ離れていたり、特定の誰かにだけ有利な内容だったりした場合、驚きを隠せないのではないでしょうか。「あの時、父はすでに認知症が進んでいたはずなのに、自分の意思で書いたのだろうか」といった不信感は、相続において少なくない問題です。
本記事では、遺言書の内容に納得がいかない方のために、以下の内容を中心に解説します。
- 遺言能力の定義や判断基準
- 裁判所で重要視される証拠
- 遺言書を無効と主張するために、どのような準備が必要か
あわせて、具体的な解決の糸口も提示します。
目次
遺言能力の有無を判断する2つの要件とは?【遺言が無効になるケース】
遺言能力の有無を判断する際には、法律が定める2つの要件を確認する必要があります。
満15歳以上であること
有効な遺言を行うためには、満15歳に達していなければなりません。民法では、15歳に達した者は遺言をすることができると定められています。
この規定には、遺言という行為の特殊性が反映されています。通常の契約などの法律行為には原則として行為能力が必要であり、未成年者が単独で行うには親権者などの同意を要します。しかし、遺言は本人の死後に初めて効力が発生するものであり、他人に損害を与えるリスクが低いため、一定の判断力が備わる15歳に達していれば、親の同意なしに自分の意思だけで行えるとされています。たとえ遺言書の内容が立派だったり形式を整えたりしても、14歳の子どもが書いた遺言書は法的に無効です。
意思能力があること
有効な遺言を行うためには、意思能力が必要です。意思能力とは、自分が行った意思表示によって、どのような法的結果が生じるかを正しく理解できる能力を指します。一般的に7歳から10歳程度の判断能力が目安とされています。遺言作成時に、自分がどのような財産を持っていて、それを誰に与えるとどのような法的結果が生じるかという因果関係を正しく理解し、判断できる状態が必要です。それがなければ、遺言を本人の真意とみなせない可能性が高いです。
この意思能力の有無は、遺言書が有効か無効かを左右するため、高齢者の相続において特に争われやすいポイントとなります。認知症を患っている場合、今日は何曜日か、ここはどこかといった基本的な認識から、自身の財産の全体像の把握、さらには遺言が及ぼす親族間の影響の予測に至るまで、総合的な精神能力が問われるからです。
単に医師から認知症の診断名がついているかどうかだけでなく、その遺言の内容が、本人の当時の認知レベルで理解可能な範囲だったかという相対的な視点で判断されます。意思能力は遺言の有効性を左右するカギとなるケースが多いです。
裁判所はどこを見る?遺言能力を判断する4つのポイント
遺言能力の有無を巡る争いにおいて、裁判所は、遺言能力の有無について、断片的な情報だけで結論を出すことはありません。実務では、主に4つの視点から遺言者の状態を総合的に分析し、遺言能力があったかどうかを判定します。
精神上の障がいの有無、内容、程度
精神上の障がいの有無や内容、程度といった医学的な客観データは、遺言能力(意思能力)の判断における重要な基盤になります。認知機能の低下が医学的に証明されていれば、それが意思能力の欠如を推認させる強力な根拠となるからです。
具体的には、医師によるカルテの記載、長谷川式認知症スケール(HDS-R)、MMSE(ミニメンタルステート検査)といった知能テストの結果が詳細に分析されます。例えば、MRI検査で脳の萎縮が顕著に見られたり、幻覚や妄想といった周辺症状が頻発していたりする場合、合理的な判断を下す能力は著しく損なわれていたとみなされます。ただし、医学的な数値はあくまでも一つの指標であり、点数が低いからといって直ちに遺言書の無効が確定するわけではなく、他の要素との組み合わせで評価されるのが実務の通例です。
遺言書作成に至る経緯
遺言書が作られるまでのプロセスに不自然な点がないかは、厳しく精査されます。本人の自発的な意思ではなく、特定の相続人による誘導や不当な干渉によって書かされた可能性があるためです。
例えば、長年介護をしてきた長女がいる一方で、突如として介護に介入し始めた次男が遺言作成を主導したケースです。
その結果、次男に全財産を譲るという内容になっていた場合、作成経緯は不自然だと判断される可能性があります。遺言書作成の背景を明らかにすることが、遺言の真意を問う上で不可欠です。
遺言書作成前後の状況
遺言書を書いた当日だけでなく、その前後の期間における遺言者の日常生活の様子は、重要な判断材料となります。特定の知能テストの瞬間的な結果よりも、日々の言動の積み重ねの方が、その人の真の判断能力を如実に反映していることが多いためです。具体的には、以下のものが証拠として用いられます。
- 自分の財産や親族の顔を正しく認識できていたか
- 銀行での手続きを一人でこなせていたか
- 妄想や幻覚によるトラブルが頻発していなかったか
これら日常的な生活能力の維持状況が、医療データと組み合わされることで、遺言能力の有無を決定づける証拠となります。
遺言書の内容
遺言書の中身そのものが、作成者の認知能力と整合しているかどうかが検証されます。あまりに複雑な遺言内容は、認知機能が低下した本人には理解不可能なはずであり、他人が作成した疑いが強まるためです。
妻にすべて相続させるなど、内容が極めて単純であれば、認知機能の低下があったとしても理解可能と評価され、有効性が認められやすい傾向にあります。対照的に、多くの不動産を細かく指定し、さらに税金対策や遺留分まで計算されたような複雑な内容である場合、それを指示・理解するには極めて高度な遺言能力が要求されます。また、それまでの人生観や家族関係と矛盾する不自然な内容である場合、能力不足や外部の干渉が強く疑われる可能性があります。
遺言能力に不安がある場合の対処法は?
親が認知症気味で、作成しようとしている(あるいはすでに作成された)遺言書の有効性に疑問がある場合、手遅れになる前に対処する必要があります。遺言を無効にするためには、遺言能力がなかったことを示す医学的な客観証拠の確保が出発点となります。
医師の診察を受ける
遺言書作成と同時期に専門医による認知機能検査を受けることは、有効な対策になり得ます。裁判実務でも、長谷川式認知症スケール(HDS-R)などの検査結果が、遺言能力の判断材料として参照されることがあるためです。
この検査は30点満点で、見当識や記憶力を測定します。一般に一定の目安は語られますが、点数だけで遺言能力の有無が決まるわけではなく、医療記録や当時の生活状況、遺言内容などとあわせて総合的に判断されます。遺言作成の直前、あるいは直後にこの検査を受けておくことで、当時の本人の状態を法的に有効な形で数値化して残すことができます。
医師から診断書をもらう
検査数値だけでなく、医師による診断書を取得しておくことも重要です。単なる点数比較だけでなく、本人が自身の財産の処分について理解し、意思表示ができる状態であるかという医師の総合的な判断が、裁判所において非常に重く受け止められるためです。
医師に対し、遺言書を作成するにあたっての判断能力の有無を確認したいと伝え、その時点の精神状態についての意見を記載してもらうことが重要です。
公正証書遺言を活用する
遺言作成における紛争リスクを最小限にするには、公正証書遺言が有効です。ただし、公証人は医学の専門家ではないため、遺言者の認知能力の欠如を見逃すリスクがある点は理解しておきましょう。
公証人は、作成時に遺言者と面談し、口頭でのやり取りを通じて意思能力を確認します。しかし、認知症の方には一時的に普通に会話ができているように見える現象があるため、短時間の接触では判断能力の欠如を見抜けないことがあります。実際、公正証書遺言であっても、後の裁判で当時の詳細な医療記録が提出され、遺言能力なしとして無効にされたケースがあります。
遺言能力の存否に関する判例を紹介
実際の裁判において、遺言能力の有無がどのように判定されているのか、具体的な事例を見ることで、その判断の分かれ目がより明確になります。
遺言能力が否定された判例
長谷川式スケールの点数が極端に低い場合や、遺言内容が本人の精神状態と矛盾している場合、遺言は無効と判断されます。
過去に、長谷川式スケールで17点という中等度の点数でもノートに記録されたお金を盗まれたという妄想の内容が、遺言の内容を歪めていると判断され、無効とされました。これは、数値以上に具体的な周辺症状が重視されることを示しています(東京高裁令和元年10月16日判決)。
遺言能力を肯定した判例
認知症の診断があっても、日常生活に一定の秩序があり、遺言内容が合理的であれば、有効と認められるケースもあります。
長谷川式スケールが15点という点数であっても、日常生活の状況や遺言内容が自然で合理的と評価できる事情がそろえば、遺言能力が肯定されるケースもあります(大阪高裁平成19年3月16日判決)。
遺言能力に不安があれば、弁護士に相談・依頼を
認知症などを理由に「遺言能力がない」と疑われる遺言書の問題を解決するには、感情的な議論を避け、法的な手続きを冷静に進める必要があります。遺言無効を主張するには、専門的な証拠収集と交渉が不可欠です。
弁護士照会を利用して証拠収集ができる
弁護士は、業務遂行のために弁護士法第23条の2に基づく照会制度(23条照会)を利用して、必要な情報の報告を求めることができます。これにより、遺言者が亡くなる直前の詳細なカルテや、介護認定の際の調査員による具体的な聞き取り内容などを公的に取り寄せることが可能になります。
調停・訴訟の準備を任せられる
話し合いで解決しない場合、調停や訴訟を検討しなければなりません。弁護士に依頼することで、煩雑な書面作成や、相手方との交渉を任せられます。
遺言が無効になった後の処理を任せられる
遺言が無効になった後のことを見据えて計画を立てる必要があります。具体的には以下の事例が発生する可能性が考えられます。
- 古い遺言書の復活
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
まとめ
本記事では、遺言能力の基本から実務における判断基準、納得できない遺言書への具体的な対処法を解説しました。
もし、手にした遺言書に強い疑問を抱いているのなら、まずは冷静に当時の医療記録や介護記録を整理することから始めてください。
相続は単なる金銭の分配ではなく、故人の意思を確認し、残された家族が納得して前を向くための大切なプロセスです。弁護士の助けを借りながら、公平な相続を実現しましょう。
ネクスパート法律事務所には、相続全般に実績のある弁護士が在籍しています。初回相談は30分無料ですので、遺言書に疑問を抱いている方は一度ご相談ください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。